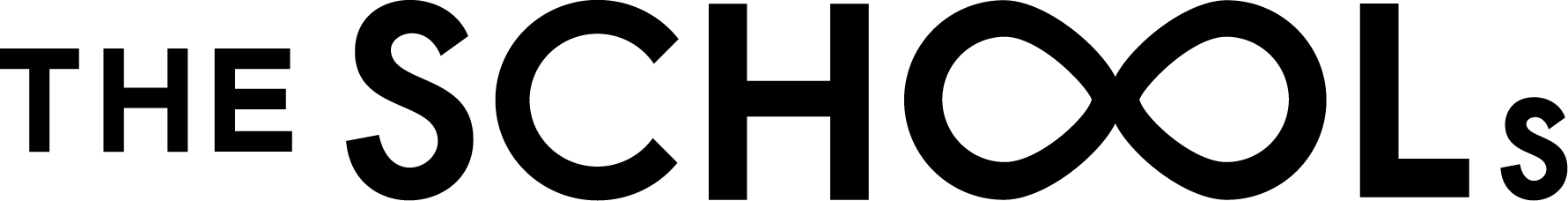2021.08.30
教員の質の低下を防げ
教育ジャーナリスト 野原 明
夏真っ盛り、公立小中学校の教員採用試験の季節を迎えた。このところ、教員志望者が減少の一途をたどり、この春採用された公立小学校教員の競争率は過去最低の2.6倍に止まったという。このため、地方の教育委員会は教員志望者を集めるために様々な条件緩和を試みている。しかし、これでは教員の質を低下させるだけであり、教員の質を低下させないための方策を考えなければならない。 この春採用された公立小学校の教員について、47都道府県と20の政令指定都市等を対象に調べた朝日新聞の調査によると、受験者数が4万3200人に対し採用者数は1万6500人で、採用倍率の全国平均は2.6倍。最低だった前年度の2.7倍を下回った。また、公立中学校の採用倍率の全国平均は4.3倍で、過去最低だった1991年度の4.2倍に急接近しており、前の年度の5.0倍から大きく低下している。 これは教員が大量に退職する時期が続いて新規採用の定員が増えたことに加え、教員の長時間労働の実態が明るみに出て、学生が教職を敬遠する動きが広がっていることに原因があると見られる。文科省の2016年度の調査によると、小学校教員の約3割、中学校教員の約6割が、「過労死ライン」とされる月80時間以上の時間外労働をしていることが分かっている。 ところが、地方教育委員会はこの課題への対応より、いかに受験者を増やすかの対策に熱心で、様々な選考方法の緩和策に知恵を絞っているようだ。実例をいくつか拾ってみよう。ある政令指定都市では、来年度実施の採用試験から筆記試験と面接を省略する特別選考方式を導入するという。教育実習の評価と県内の大学からの推薦だけで採用を決めるというのだ。筆記試験と面接を省くのは受験者の基礎学力を確認しないことでもある。 また、ある県教育委員会は来年度から「前年度試験実績者」に向けた特別選考を新たに設け、今年度筆記の1次試験に合格し、2次の模擬授業などで不合格になった人は、来年度の試験で1次試験が免除される。免除対象の一般教養や教科専門試験は対策に時間がかかり、民間企業などに勤務しながら教員試験に再挑戦しようとする人には足枷になっているという。 今年度実施の試験から、県外で教諭として3年以上働いた人には1次試験を全部免除する優遇措置を始めた県もある。 筆記試験で一般教養や教職教養を免除することが極めて危険であるのは、長年採用試験に関わってきた筆者が強く感じてきたことである。教職教養の筆記試験の成績が共通して低いこと、なかでも学習指導要領に関係した問題では驚くほど点数が取れないことを知り尽くしているだけに、これらの試験の免除には断固反対である。 また、コロナ禍との関連で1次試験の集団面接を取り止める県、2次試験の模擬授業を実施しない県、1次試験の一般・教職教養試験などを取り止める政令指定都市もある。単に志願者を増やそうというだけの試験の免除は、教員の質の低下を招くだけという指摘があることを忘れてはなるまい。「教育は百年の大計」といわれている。競争率を高めるために教員の質を低下させるのは本末転倒と言わざるを得ない。 教員志望の学生を増やし、質の高い教員を獲得するには、弥縫策を取るのではなく、学生をして教職を選ばせる魅力を高めることが唯一で、最高の対策であることを、国や地方教育行政は認識すべきであろう。それには学校の長時間労働を解消し、教員を雑事から開放して授業に専念できる環境を早急に整えることが喫緊の課題である。国や地方の教育行政が、道を誤ることなく課題を解決してくれることを望むばかりである。
野原 明
1958年京都大学卒。記者として放送界に入り、83年NHK解説委員(教育・文化等を担当)、93年定年退職。2001年まで部外解説委員。93年文化女子大学教授、2000年同大学付属杉並中高校長兼務。11年退職して文化学園大学名誉教授、同大杉並中高校名誉校長に。現在はフリーの教育ジャーナリスト。マスコミと学校現場を経験した教育評論が特色。
記事一覧へ