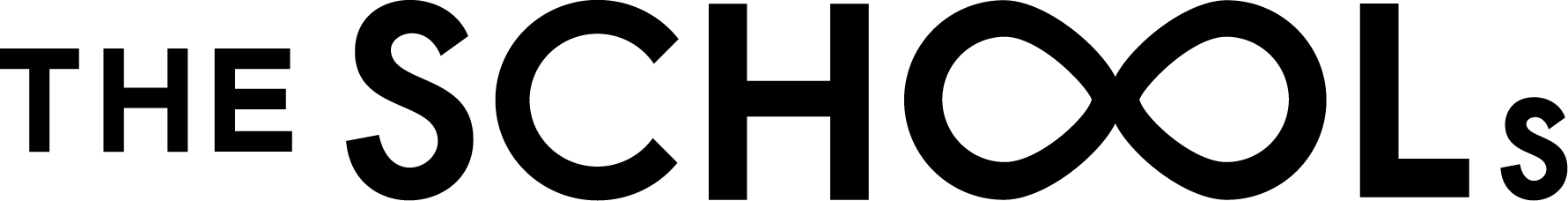2021.08.30
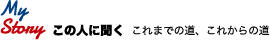

人生のなかで迷う時間を
大切にしてくれてありがとう
駒場東邦中学校・高等学校卒業生
シンガーソングライター/音楽プロデュサー
臼井 ミトンさん
作詞・作曲からボーカル、ギター、ピアノ、さらに他アーティストのプロデュースや編曲アレンジまで、幅広い音楽活動を展開する臼井ミトンさん。駒場東邦中学校・高等学校を卒業後、アメリカに渡り、アーティスト活動をスタートさせました。中高時代の恩師である同校の小家一彦校長も交え、これまで歩んできた道のりを語っていただきました。

劣等感を抱えつつ、
バンド活動に明け暮れた中高時代
「今思うと、誰かに止めてほしかったですね」。18歳で単身アメリカに渡った当時を、冗談半分でこう振り返る臼井さん。どのような中高時代を過ごしたのでしょうか。「小学4年生くらいのときに駒場東邦中高の文化祭を見に来たんですが、生徒が自分たちの好きなことをやって盛り上がっている様子がすごく楽しそうで、絶対にここに入りたいと思ったんです。塾で友だちとワイワイ勉強するのも楽しくて、余裕をもって合格したつもりでいました。でも、いざ入学してみると、周囲のハイスペックさに圧倒されて…。僕自身中1~中2の間は成績も悪くなかったと思うのですが、授業中は寝ているのにテストではめちゃくちゃ良い点を取るヤツとかがいて(笑)。勉強ではこいつらに太刀打ちできないなという劣等感みたいなものは早い段階から感じていましたね」 そんな臼井さんを魅了したのが、音楽でした。幼少期からチェロを習い、小学校ではドラムにハマり、お姉さんの影響で流行りのポップスも聞いていました。中学に入学すると、軽音楽部(当時は同好会)に入部。当時顧問を務めていたのが、小家先生でした。「中学校では絶対にバンドをやると決めていました。中学1年生のバンドは秋の文化祭でお披露目するんですが、ドラムの自分とお客さんとの間に他のメンバーがいるのが許せなくて(笑)。それで、ボーカルとギターを始めたんです。先輩と駅前で路上ライブをしたり、文化祭でゲリラライブをしたり…楽しかったですね」 高校2年生のときには部長に。それまでは部員の間の温度差が大きかったそうですが、「臼井くんが部長になってから、ちゃんと練習する部になった。あの代から軽音楽部は変わっていった」と小家先生は振り返ります。「職員室の小家先生の机の隣のスペースに入り浸っていましたね…」と当時を懐かしむ臼井さん。部活のことから将来のことまで、小家先生とはいろんな話をしたといいます。 そして、進路選択のとき。周囲の多くが東大をはじめとした国内の難関大学を目指すなか、臼井さんはアメリカのバークリー音楽院への進学を決意したのです。「バークリー音楽院はジャズに特化した音楽学校なんですが、高校時代に個人的にアメリカの古いブルースに傾倒していたこともあり、アメリカで音楽をやりたいなと。ただ、絶対に行きたいんだ、日本じゃなくアメリカで音楽をやるんだというパッションがあったかというと、それは正直なかった。今思うと、みんなと同じように大学受験をして同じような道を歩むことへの反抗というか…こじらせてたなっていう思いは強いですね。学校の先生からは、反対された記憶はありません。君がやりたいんならやってみればいいんじゃないか、という感じでした。出願に必要な書類なども、準備してくださいました」


中学1年の時に軽音楽部で出演した音楽発表会にてドラムを叩く臼井ミトンさん
卒業後は渡米して音楽の道へ。
ロスで演奏活動をスタート
結果的にバークリー音楽院は入学前のサマースクールに参加しただけで辞めてしまい、臼井さんが選んだのはロサンゼルスにある音楽の専門学校でした。学校があったバーバンクはハリウッドにも近く、映画産業が盛んな街。そこで臼井さんは、学業の傍ら、ギターの演奏家として活動を始めました。「音楽ライブレストランなども多く、常に演奏の仕事がある街でした。僕はもともとロックバンド出身だったのでテクニック的にすごい演奏ができたわけじゃないんですが、高校時代に個人的に弾いていた関係でブルースの素地があったので、重宝されました。また、アメリカのテレビ番組では出演者の人種の多様性が重視されるので、日本人がいるとバランスがいいと採用され、カリフォルニア州内の高校をまわる素人発掘番組のバンドメンバーを務めたこともあります。さまざまなシーンでさまざまなジャンルの曲を演奏する機会を得られたのは、幸運でした」 順調だったアメリカでの生活でしたが、渡米して2年ほど経った頃、臼井さんは疑問を感じるようになりました。「もともと自分で作った曲を演奏したい、歌いたいという思いでバンドをやっていたので、このままだと演奏だけになってしまうなと…。ノンネイティブが英語で歌詞を書いて英語で歌うというのは、実はアメリカの音楽シーンではものすごくハードルの高いことなんです。英語は中高時代から好きでアメリカでも日常生活に困ることはありませんでしたが、英語に親しめば親しむほど越えられない壁もあると感じていて、歌詞を書くならやっぱり母国語である日本語で書きたいという思いも強かったですね」

卒業アルバムに掲載された軽音楽部の44回生と顧問の先生方(右から3 番目が臼井さん、右端が小家先生)
持ち前の行動力で、
海外のミュージシャンとレコーディング
思い立ったら即行動の臼井さん。「思いつきのように帰国した」と当時を振り返ります。日本に戻ってからは、英語力を活かして航空関係のテレフォンオペレーターやコールセンターでアルバイトをしつつ、音楽活動も継続。高校時代のアルバイト先で身につけたデザインのスキルと持ち前のセンスで、音楽関係のグラフィックデザインの仕事も手がけていました。一方、日本ではライブミュージックに触れる機会が少なく、「飢えていた」という臼井さん。食事をしながらライブが楽しめるブルーノートやコットンクラブに通ったり、海外のミュージシャンのインストアライブやサイン会に足を運んだりしていました。そうしたなか、ある出会いが臼井さんを再びアメリカへと引き寄せたのです。「あるとき、アラバマ州のマッスル・ショールズというソウルミュージックのメッカのようなスタジオがある街で活躍する、ベーシストのデヴィッド・フッドという人が来日していて、インストアライブとサイン会に行ったんです。サインをしてもらう際に、自分も音楽をやっているんだと言うと、社交辞令でしょうけど、じゃあいつかライブに呼んでくれよ、一緒にやろうよ、みたいなことを言われて。僕が自分で宅録でアルバムを作り始めていると言ったら、マッスル・ショールズにはもう誰も来なくて仕事がない、マッスル・ショールズで録ればいいと、名刺をくれたんです。後日メールをしたら、来ていいと言うので、ノートパソコンを持ってマッスル・ショールズに向かいました」 臼井さんの行動力には驚かされますが、実はデヴィッド・フッド以外にも、同じようにライヴ会場で声をかけ、レコーディングへの参加の約束を取り付けていたミュージシャンがいたのです。「マッスル・ショールズでの録音を終えてすぐにニューヨークへ飛びました。ベーシストのウィル・リーに弾いてもらうためです。彼にデヴィッド・フッドの話をしたら、あの人は神だ、おまえはわかっているやつだと興奮しだして(笑)。その場でデヴィッド・フッドに電話して、二人をつなぎました。さらにレコーディング中はウィル・リーが『この曲はあいつにギターを頼んだらどうだ?』という具合にニューヨークのミュージシャンをたくさん紹介してくれて、またそこから広がって、まさにRPGのような感じ(笑)。アメリカ滞在期間は予定よりどんどん延びて、ユースホステルを定宿に、ミュージシャンの家にもよく泊めてもらいました」

臼井さん(写真左)とデヴィッド・フッドさん(写真右)
旅する宅録アーティストとして
音楽業界で話題に
宅録機材を抱えてミュージシャンに会いに行き、行く先々で演奏を録っていた臼井さん。ときには著名ミュージシャンのライブツアーを追いかけて、ホテルの部屋で録音したこともあったそうです。持ち歩きができないマイクスタンドは、毎回、その街で一番安いものを購入。音源は持参したノートパソコンで録音・編集しており、当時はミュージシャンから「そんな装備で音楽が作れるのか」と不安がられたといいます。 こうして名だたるミュージシャンの宅録を重ねて2011年に完成したのが、ファーストアルバム「Singer Traveler Songwriter」。臼井さんはその後も同様の手法で制作を続け、現在までに3枚のアルバムを出しています。ライブやツアーも全国で行うなど、活発な活動を展開。その特殊な手法が音楽業界で話題になり、制作やアレンジを依頼されることも増えていきました。「なんかすごいやり方で作っているヤツがいるぞと(笑)。子どもの頃から自分で何かを作ることが好きだったので、僕にとってはその延長のような感じです。なかなか思い通りにいかないことも含めて、録り直しの効かない音源をどう構成・編集するかというのが面白くて。僕の曲を聞いたアーティストからこんなふうにアレンジをしてほしいと依頼されることから始まって、少しずつプロデュースやアレンジの仕事が増えていきました。音楽を生業にできたのは、ここ5年くらい。音楽業界全体がお金をかけて大型スタジオで録って…みたいな時代ではなくなってきていることも、宅録派の自分には追い風になっていると思います。さらにコロナ禍でスタジオ収録やライブが難しくなったことで、宅録で音源を作ろうというミュージシャンが増えて、ありがたいことに忙しい日々を送っています」

臼井さん(写真右)とウィル・リーさん(写真左)

自由にやらせてもらえたから、
ものづくりへの意欲が保てた
現在は、ラジオ番組のパーソナリティを務めるなど、活躍の幅をさらに広げている臼井さん。改めて半生を振り返るなかで、こんなことを感じたと言います。「中高6年間のことも、なんだか自分じゃない人の人生を見ているような感じなんですよね。小学校時代、中高時代、アメリカ時代、帰国してから…と、分断されているというか。それでも、小学校で初めてドラムに触れたことも、中高時代の軽音楽部での活動も、今の自分のベースになっているわけですから面白いですよね。今でも、高校時代に赤点を取って追い詰められている悪夢を見ますしね(笑)。中高時代は自分がやりたいことと学校のアカデミックな勉強との間のギャップに苦しんだ時期でしたが、やりたいことを自由にやらせてもらえたから、自分の中のクリエイティブな感性を発揮したいというモチベーションを保てたんだと思います」 最後に臼井さんが小家先生に伝えたのは、こんな言葉でした。「人生のなかで迷う時間を大切にしてくれた先生、学校には、本当に感謝しています」。


記事一覧へ