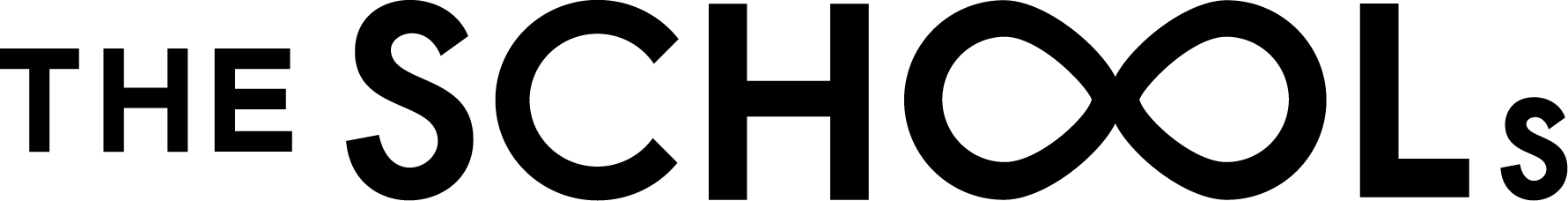2021.10.30
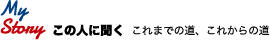
医師として、女性として、
傍らで支える存在でありたい
傍らで支える存在でありたい
竹添 豊志子さん
横浜雙葉中学高等学校を卒業して医師になり、小児外科医として活躍してきた竹添豊志子さん。現在は一時的に小児外科医療現場を離れ、東京大学大学院医(博士課程)で栄養学の研究にあたっています。3児の母でもある竹添さんに、これまで歩んできた道のりを語っていただきました。

十字は切らない、聖歌は歌わない!
そんな生徒にも寛大だった先生たち
竹添さんに横浜雙葉中学高等学校の受験を勧めたのは、母親でした。「そこに私の意思はなかった」と振り返ります。「今となっては横浜雙葉で6年間を過ごして良かったと思うことが多々ありますが、当時は公立の中学校に行きたかったし、女子校は嫌だったんです。でも、カトリック校出身の母はカトリックの女子教育に傾倒していて、娘をどうしても横浜雙葉に入れたかったようです。2つ年上の姉も横浜雙葉に通っていました。母はよく、『長い人生で、女性だけのなかで生きるのはこの6年間だけなんだから、いいじゃない』と言っていました。当時はその意味がよくわかっていませんでしたが、今になると確かにそうだと思います。女子だけだからこそ甘えが許されない、なんでも自分たちでやらないといけないので、鍛えられますから」横浜雙葉のほか、国立大の附属校にも合格。竹添さん自身は国立に行きたかったものの、「母が早々に横浜雙葉の入学手続きを進めていた」と苦笑します。不本意な気持ちで入学したものの、勉強や学校生活は概して楽しく、ボーイッシュで運動神経も良かった竹添さんは、生徒たちの憧れの的になりました。そうしたなか、竹添さんのなかにはモヤモヤした思いが少しずつ募っていきました。「女子校って、男の子扱いされる子が出てくるんですよね。そう扱われること自体は構いませんでしたが、エスカレートしてストーカー的なことをされたり、嫉妬心から人間関係がぎくしゃくしたり…。そういうことがあって、疲れるなあと思っていました。さらに、信仰心の問題もありました。自分で考えた上で教えに共感して、というわけでもなく、言われるままに十字を切ったり聖歌を歌ったりするのって、形式的だし洗脳っぽいし、なんかおかしい…と違和感を感じていたんです。それが次第に嫌悪感にまでなって、高校生のときに、『私は十字は切らないし、聖歌も歌わない!』と宣言したんです。純粋さゆえに多感な時期でした。いろんなことが重なって、中高時代はいわゆる“いい生徒”ではまったくなかったですね」「十字は切らない・聖歌は歌わない」と宣言した竹添さんに、先生たちは強制をしなかったと言います。「規則や指導は細かい学校でしたが、私のような生徒にも寛大だった」と振り返ります。

中高時代の教室にて

中高時代に所属していたハイキング部の合宿にて
周囲からの刺激もあり、
高3で医学部受験を決意
医師を目指して医学部進学を決めたのは、高校3年生とギリギリのタイミングでした。中学生の頃から医療系の仕事に就きたいという思いはあったものの、「自分の成績では医師を目指すのは無理だろうと思っていた」と言います。「周囲に医学部を目指す子が多かったことが、刺激になりました。高校生になってからは成績も上がってきたので、私でも行けるかもと思うようになりました。さらに、大腸ガンを患っていた祖母の主治医の先生が素敵だったこともあり、医者になろうと決意しました」高校・大学で教員をしていた両親は当初は反対していましたが、竹添さんの揺るがない思いを理解し、最後は応援してくれることに。その後亡くなった祖母の、「女性でお医者さんなんて、かっこいいじゃない」という言葉に背中を押されたと、竹添さんは懐かしみます。「当時の私はツンケンしていたので、高校の先生には、進路のことをあまりフランクに相談することはなかったですね。医学部進学者の多い学校なので、医学部を受けると告げると、すんなりと受け入れてくれました。私は親戚に医者がいないので、医学部などの情報を集めるのには苦労しました。仲の良い友だちが医学部を目指していて、彼女のお父さんが開業医だったので、その子にいろいろと相談していました。今思うと、医学部を目指すには恵まれた環境だったと思います」
医学生として葛藤する思いを、
高校時代の恩師に綴る
1年の浪人を経て、昭和大学医学部に進学。念願の医学生生活でしたが、解剖実習や手術見学、病院実習などを経験するなかで、竹添さんのなかに葛藤が生まれていきました。「最初は、ご遺体の解剖や手術、患者さんの死が、すごくショックでした。でも、食事も喉を通らないくらいだったのが、数ヶ月も経つと、少しずつ慣れていきます。そうするなかで、慣れないと医師は務まらないという思いと、慣れてしまっていいんだろうか、目の前で患者さんが亡くなっても自分は何も感じなくなってしまうんだろうか…という不安や恐怖があって…」竹添さんが揺れる思いをぶつけたのが、高校2年次の担任だったM先生でした。「M先生は、なぜかわからないんですが、高校時代から私のことを気にかけてくださって。卒業後も手紙のやりとりが続いていて、医学生の頃は葛藤を綴った手紙を先生に送っていました。先生からは、『大いに悩んだらいい。いつかきっと、答えが出るから』とお返事をいただいたことがとても印象に残っています」医師になった今、その答えは出たのでしょうか。竹添さんは、こう答えます。「私は今でも、自分の患者さんが亡くなったときに涙を流してしまうことがありますし、手術で執刀するときに手が震えることもあります。医師としてそれではダメだという考えもあるかと思いますが、私はときには感情に負けることがあっても、人間らしくていいんじゃないかと思うようになりました。無理に慣れる必要はないし、逆に、無理に慣れないでいる必要もない。そう思っています」

大学時代にボランティアで活動していた北岳診療所にて

大学時代にボランティアで活動していた白馬診療所にて
医師としてのキャリアを積みつつ、
結婚・出産・育児を経験
外科医としてキャリアをスタートした竹添さん。女性の医師が活躍しており、かつ、入局後に専門を選ぶ余地があった東京大学病院の外科に入局しました。「最初の3年間は消化器外科医として勤務した後、専門を小児に絞り込み、小児外科医として勤務するようになりました。小児外科医は数が少ないので、東大病院の医局に属したうえでいろんな病院に派遣されます。東大病院のほか、国内外から重篤な病気の子どもが集まる国立成育医療研究センターで働いたこともあります。東大病院の医局の医師は、ほぼ全員が大学院で研究をすることになっていて、そろそろ研究をしてみてはどうかと言われたのが3年前。そこで、4年間の計画で、東京大学大学院に進学しました。医師としてのキャリアを歩む傍ら、プライベートでは結婚・出産・育児と大きなライフイベントを経験してきました。「結婚したのは30歳のとき。当時は東大病院で働いていました。子どもは欲しかったのですが、タイミングに悩んでいました。妊娠するとレントゲンが浴びられなくなるため仕事に支障が出ますし、大きなお腹で手術ができるだろうかという不安もありました。第1子は33歳で妊娠し、幸い体調も良かったので、産休直前まで手術をしていました。当時は成育医療研究センターに勤務していたのですが、病院の敷地内に宿舎も保育所もあるという環境だったので、育休は取らずに復職。2歳違いで第2子を妊娠・出産しました。そのときは東大病院に戻っていて、24時間開室の院内保育園があったので、第2子出産後も当直を勤めていました」その後、現場を離れて大学院で研究することが決まると、「3人目を考え始めた」と言います。「もともと子どもは3人欲しいと思っていたので、大学院在学中ならちょうどタイミングがいいかなと思い、夫と相談して決めました。経済的にやっていけるかなど綿密に計算しましたが、本当に産んで良かったです。子どもたちに無理をさせているという罪悪感がないといえば嘘になりますが、自分の母が働く姿を見てきたこともあり、働かないという選択肢は自分の中にはありませんでした。夫とはパートナーとして対等な関係です。中高時代に聞いた『配偶者としての生き方』という話がとても印象に残っているんです。リーダーシップを取るのでも後ろを付いていくのでもなく、傍にいて支える。女性として夫に対しても、医師として患者さんに対しても、そういう存在でありたいと思っています」

医学部実習班のメンバーと

研究や子育てを経験した
自分だからできることがある
現在は、6歳、4歳、2歳と3人の子どもを育てながら、研究に勤しむ日々を送ります。研究のテーマは、食事と栄養。希少な疾患の子どもに接するなかで、食事・栄養の大切さを実感し、医師としてより深く学びたいと感じたと言います。「一般的に、医学部の履修科目には栄養学はなく、医師の多くは栄養について詳しくありません。私自身もそうだったのですが、病院の栄養管理チームに所属した際に、食事・栄養を変えることで病気の子どもの体調がガラリと変わるのを目の当たりにし、栄養の勉強がしたいと考えるようになりました。小児外科医として得意分野がないことに悩んでもいたので、専門性をつけるいいチャンスだと思い、研究テーマに選びました。現在は、病気の子どもが食べている食事内容を栄養素レベルで測れるようなアセスメントツールの開発にも取り組んでいます」4年間の研究期間を経て、来年4月には医療の現場に戻る予定の竹添さん。研究期間中は週2回の訪問医療の仕事のみで、手術にはブランクがあるため、「正直、不安の方が大きい」と言います。それでも、「これからの医師人生において、やりたいことが大きく2つある」と目を輝かせます。「1つは、この4年間で学んだことを臨床に活かしていくこと。栄養についてはこれまで我流でやってきた部分があったので、確かな知見に基づいて判断できるようになったことは大きいです。もう1つは、患者さん一人ひとりの生活スタイルに基づいた治療方針やアドバイスをしていくこと。母として子育てをするなかで、また訪問医療で患者さんの生活の実情を知ったことで、自宅で続けられない治療だと意味がないことを痛感したのです。私は手術が飛び抜けてうまい外科医ではありませんが、研究や子育てを経験し、自分だからできること、気づける視点を養えたことで、自信がつきました」自分の手で人生の扉を開き、自分の足でしっかりと人生を歩んできた竹添さん。最後は、「自分の仕事に誇りをもって頑張っている姿を、子どもたちに見せたい。この思いを原動力に、これからも医師としてのキャリアを積んでいきたい」と力強く語ってくれました。
記事一覧へ